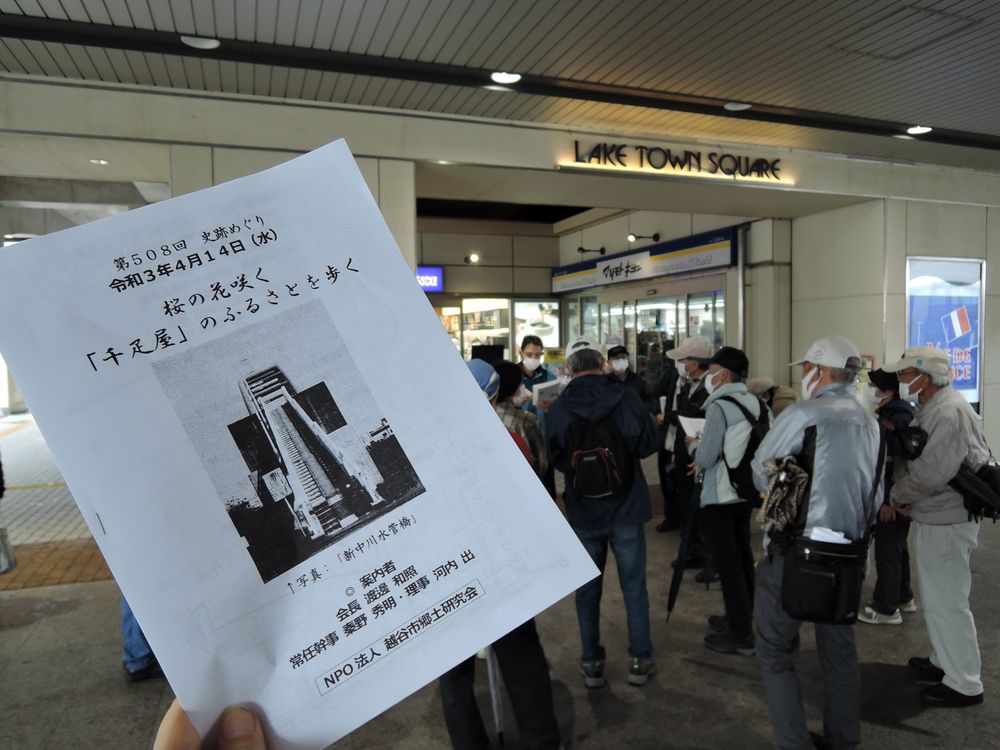荻島仲良し通り史跡めぐり
二基の石塔

二基の石塔の向かって左は巡礼供養塔。江戸後期・寛政10年(1798)造塔。右は青面金剛像庚申塔。江戸後期・天明元年(1781)造塔。
堂舎|ひやみず観音堂

堂舎は左右に分かれている。向かって左手、開き戸の奥に安置されているのは、金色の地蔵菩薩立像。右の祠(ほこら)には、石仏が二基、並んでいる。
このあたりの地は、「ひやみず」(冷水)と呼ばれ、この堂舎は、地元では「ひやみず観音堂」とも呼ばれている。
ひやみずの観音さま

賽銭箱のうしろ、向かって左は、観世音菩薩を主尊とした念仏供養塔。通称「ひやみずの観音さま」。江戸前期・寛文5年(1665)造塔。右は、江戸中期・正徳2年(1712)の一石六地蔵(いっせきろくじぞう)
新旧写真

ひやみず観音堂今昔
ひやみず観音堂の昔と今の写真を上下に二枚並べた(上の写真)
上段の白黒写真は、今から50年前、昭和50年代に撮影されたと思われる堂舎と二基の石塔。出典は越谷市デジタルアーカイブ(※5)
下段の写真は今回、ボクが撮影した同じ場所からの風景。50年前は、堂舎の周囲は樹木が生い茂っていたが、今は伐採されてすっきりしている。
※5 白黒写真の出典…越谷市デジタルアーカイブ「北後谷の堂舎」
二基の石塔と堂舎がある「ひやみず共同墓地」については別記事で詳しく解説している。
関連記事
越谷市南荻島の南端・末田用水に架かるひやみず橋そば(荻島仲良し通り沿い)の共同墓地にある石仏と石塔を調べた。
ひやみず橋と下手堰

ひやみず観音堂の20メートルほど先、右手に見えるのは、ひやみず橋と下手堰(しもてぜき)
ひやみず橋

末田大用水に架かるひやみず橋。かつて「ひやみず」(冷水)と呼ばれた地名の名残を今に残している。
下手堰

こちら(上の写真)は下手堰。末田大用水の水量を調節している。
「下手」(しもて)は、昔の荻島村の字名(あざめい)(※6)。このあたりは「荻島村下手組」と呼ばれた。
※6 荻島村には、◇堤根組(つつみねぐみ)◇野合組(のあいぐみ)◇野中組(のなかぐみ)◇中組(なかぐみ)◇下手組(しもてぐみ)……と呼ばれる五つの字(あざ)があった。
移動

道を右折。ひやみず橋を渡る。末田大用水とは別れを告げ、荻島仲良し通りを道なりに進む。
二基の石塔

ひやみず橋から荻島仲良し通りを400メートルほど進むと、Y字路にぶつかる。右手の細い道の先(用水路脇)に、小さな石塔が二基立っている。
庚申塔

向かって左側は、文字庚申塔。江戸後期・寛政3年(1791)造塔。正面の主銘は「青面金剛」(しょうめんこんごう)
主尊不明の石塔

右側は、祠型(駒型)の石塔。主尊や主銘は不明。造塔は江戸後期・文政13年(1830)。左側面(向かって右側)に「文政十三庚寅」の銘が確認できる。
移動

荻島仲良し通りに戻って、200メートルほど歩くと、左前方の道ばたに石仏が見えてきた。
青面金剛像庚申塔

この石仏は庚申塔。江戸後期・寛政2年(1790)造立。正面に主尊の青面金剛像(しょうめんこんごうぞう)が浮き彫りされている。
新旧写真

荻島仲良し通りの庚申塔今昔
青面金剛像庚申塔の昔と今の写真を上下に二枚並べた(上の写真)
上段の白黒写真は、今から50年前、昭和50年代に撮影されたと思われる青面金剛像庚申塔。出典は越谷市デジタルアーカイブ(※7)
下段の写真は今回、ボクが撮影した同じ場所からの風景。庚申塔の後ろに広がる田園風景は、50年前と今もあまり変わらない。残しておきたい越谷の風景だ。
※7 白黒写真の出典…越谷市デジタルアーカイブ「南荻島・旧村道の青面金剛像庚申塔」
この青面金剛像庚申塔については別記事で詳しく解説している。
関連記事
越谷市南荻島の南西を通る荻島仲良し通り沿いにある江戸後期・寛政2年(1790)造立の青面金剛像庚申塔を調べた。調査日は2023年11月28日。昔と変わらぬ路傍の石仏を写真とともにお伝えする。
移動

青面金剛像庚申塔をあとに、荻島仲良し通りを道なりに進む。200メートルほど歩いた先のT字路を左折。小道を入っていくと、突き当たりに墓地がある。この墓地は明王院(みょうおういん)と称された寺院跡である。