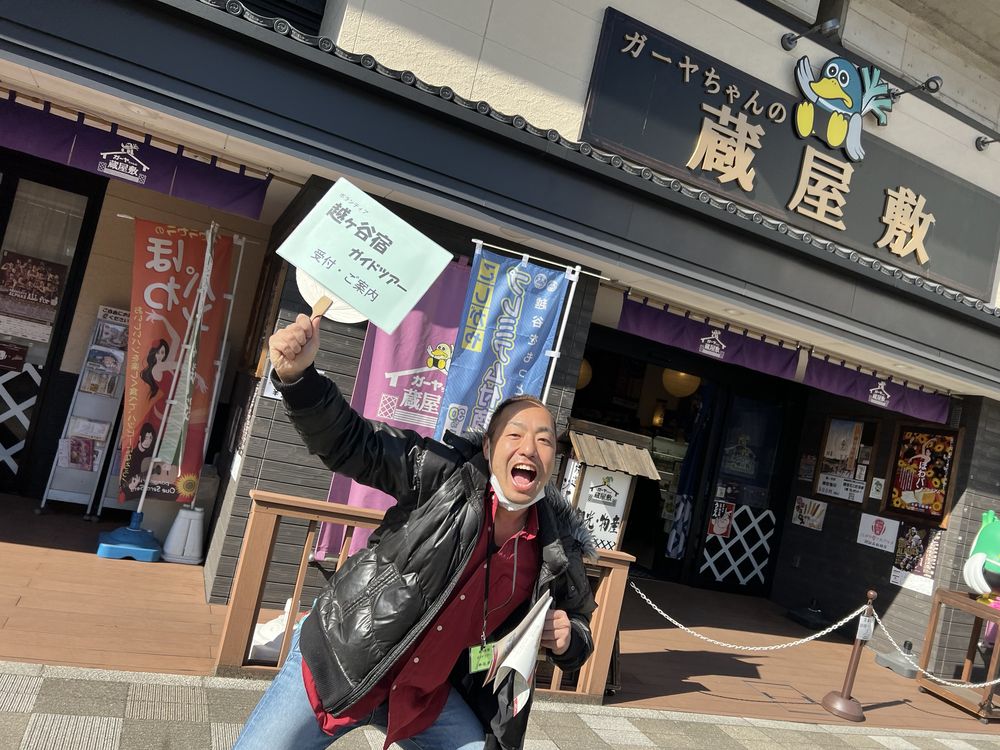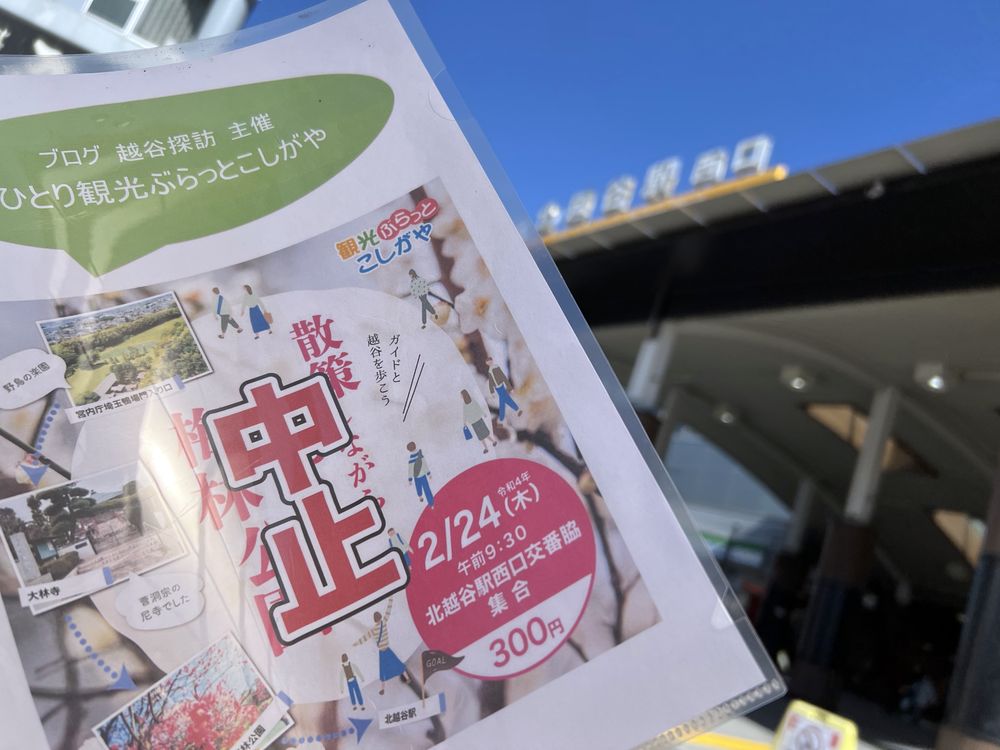2025年3月25日。こしがや市民活動連合会「三ノ宮卯之助が持ち上げた610キログラム・日本一の力石を見に行こう!」に同行。埼玉県桶川市の文化財に指定されている「桶川稲荷神社の力石」を見学してきた。
日本一の力石を見に行こう!

桶川稲荷神社の力石
本文に入る前に、予備知識として、三ノ宮卯之助(さんのみやうのすけ)と力石(ちからいし)について、簡単に触れておく。
三ノ宮卯之助

三ノ宮卯之助興行広告木版刷(越谷市立図書館蔵)※1
三ノ宮卯之助は、江戸後期、日本一の力持ちとうたわれた、岩槻領三野宮村(現在の越谷市三野宮)出身の人物。力持ちを見世物として一座を結成し、諸国を回って活躍した。
上の写真は、「江戸力持三ノ宮卯之助」と題された、三ノ宮卯之助興行一座の木版刷広告(チラシ)
※1 上掲の木版画は、2022年3月8日に越谷市立図書館で、市史資料利用の許可を事前に受け、関係者立会いのもとに「三ノ宮卯之助興行広告木版刷」を撮影したもの。無断転載厳禁。
力石

三ノ宮卯之助銘の力石|越ヶ谷久伊豆神社
力石(ちからいし)とは、江戸時代から明治時代にかけて、力比べや体を鍛えるために使われた石のこと。村いちばんの力自慢を競ったり、村落対抗の力くらべなど、娯楽としても盛んだった。
力持ち大会で優勝した人の名前や持ち上げた石の重さなどを刻んで神社や寺院に奉納された力石も見られる。上の写真は、越ヶ谷久伊豆神社にある三ノ宮卯之助の銘が刻まれた力石。重さは50貫目(約190キログラム)
それでは、当日の様子をお伝えする。
集合|春日部駅ホーム

集合場所は東武野田線・春日部駅ホーム。集合時間は午前10時。
参加人数は10人。電車を待つ間、案内役をつとめる、こしがや市民活動連合会の宮川進氏(越谷市郷土研究会・元会長)から、本日の行程について説明があった。
春日部~大宮~桶川

10時8分。急行で大宮に向かって出発。大宮でJR高崎線に乗り換え桶川へ。11時、桶川駅着。
中山道桶川宿

桶川駅東口のロータリーを進むと桶川駅前交差点に出る。左右に延びているのは中山道(なかせんどう)。交差点を左折し、中山道を歩く。このあたりが桶川宿(おけがわじゅく)の中心地だった。
江戸時代の五街道のひとつで、江戸日本橋から京都三条大橋まで、69の宿場があった。中山道六十九次とも呼ばれる。埼玉県には、九つの宿場、①蕨②浦和③大宮④上尾⑤桶川⑥鴻巣⑦熊谷⑧深谷⑨本庄……があった。
桶川宿
桶川宿は、江戸・日本橋から10里(約40キロメートル)、中山道六十九次のうち、日本橋から数えて六番目の宿場。
「中山道もの」といわれた良質の麦や、紅花(※2) の集散地(※3)として栄えた。なかでも桶川の紅花(べにばな)は、「桶川臙脂」(おけがわえんじ)と呼ばれ、多くの紅花商人によって取引された。臙脂(えんじ)とは、紅花から作った濃い紅色のこと。
※2 紅花(べにばな)…キク科の一年草。黄金色の花は、黄色や紅色の染料として使われる。
※3 集散地(しゅうさんち)…生産地から産物を集めて、これを他方に送り出す地。江戸時代、桶川は、紅花の生産地として、全国で二番目の生産量を誇った。
中山道沿いに、宿場町当時を思わせる建造物が点在している。
島村老茶舗

島村老茶舗(しまむらろうちゃほ)。江戸後期・嘉永7年(1854年)に創業した老舗茶商。170年の歴史を誇る。
現在の店舗は大正15年(1926年)、主屋は嘉永7年に建てられ、当時の姿をそのまま残している。桶川宿の面影を伝えるたいへん貴重な建物として、令和2年(2020年)に国の登録文化財(建造物)に指定された。
矢部家住宅

矢部家住宅(やべけじゅうたく)。「木半」(きはん)の屋号で穀物問屋を営んでいた。紅花の商いで財をなす。
土蔵造りの店蔵(みせぐら)は、明治38年(1905年)建造。奥の土蔵造りの文庫蔵(ぶんこぐら)は明治17年(1884年)の築造。桶川宿で現存する唯一の土蔵造りの店蔵。
往時の桶川宿の繁栄と賑わいをしのぶことのできる貴重な建造物のひとつとして、桶川市有形文化財(建造物)に登録されている。
小林家住宅主屋

小林家住宅主屋(こばやしけじゅうたくしゅおく)。木造瓦葺き。江戸時代末期ころに建てられた旅籠(はたご)。その後、材木商を営む。
宿場町当時の旅籠のたたずまいを今に伝える貴重な建造物として、平成16年(2004年)に、国の有形文化財(建築物)に登録された。
現在はギャラリー&カフェとして営業している。
昼食|手打うどん松屋