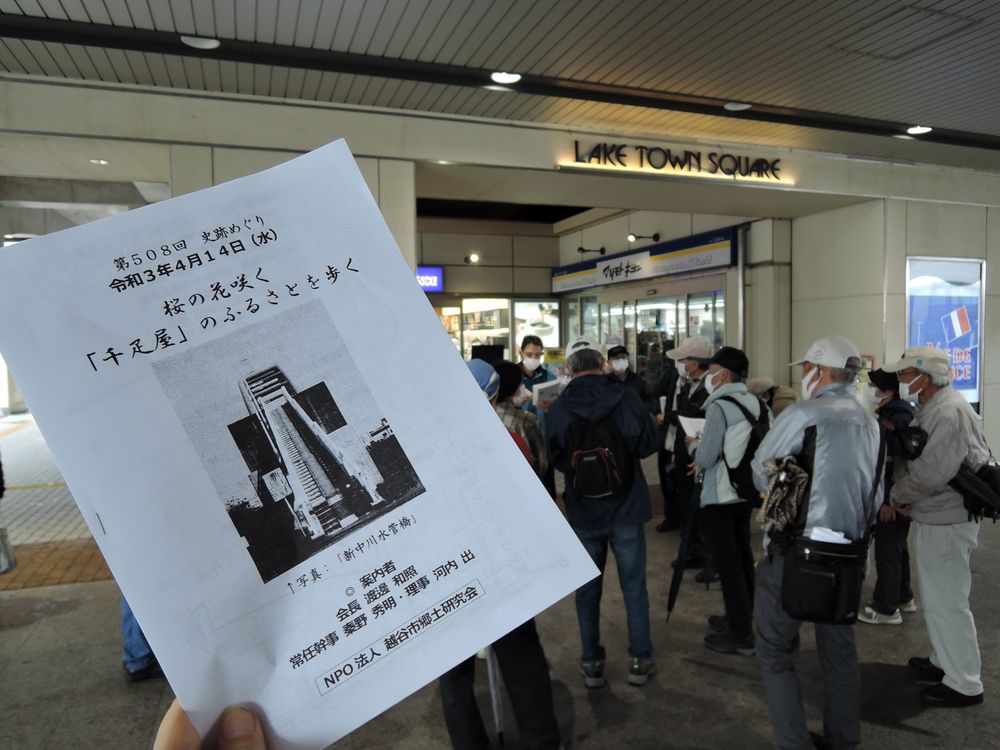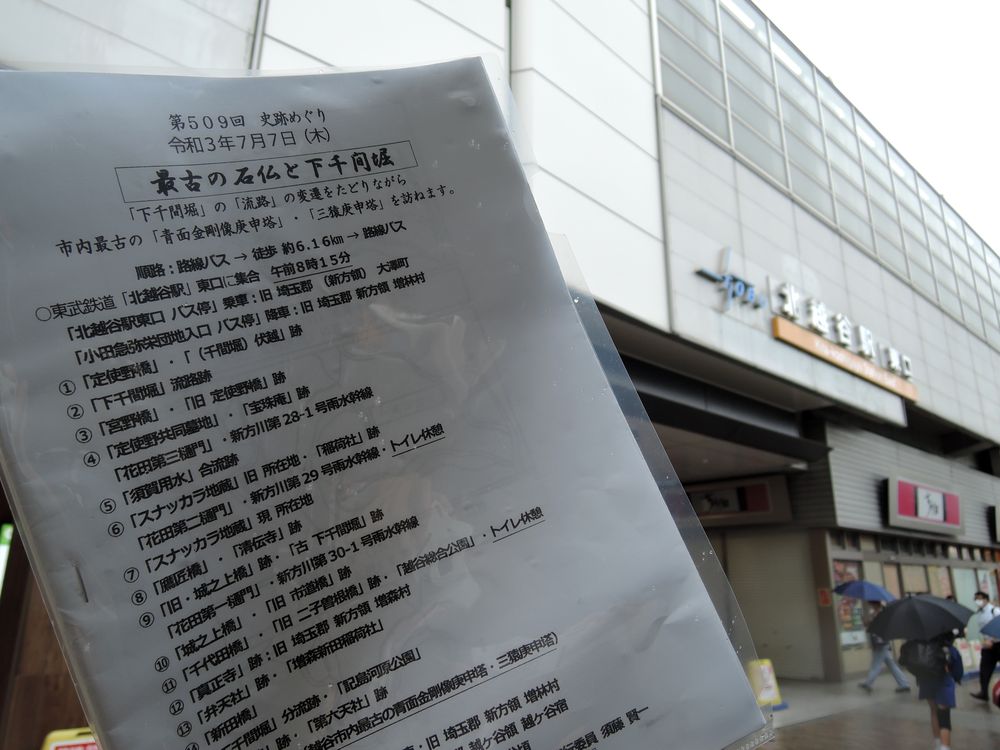2025年2月24日。越谷街道を通す末田大用水に架かる大石橋を起点に、荻島小学校まで、荻島仲良し通り沿いにある石仏や史跡をめぐった。
荻島仲良し通り史跡めぐり

荻島仲良し通りと末田大用水(※1)
荻島仲良し通りは、昭和63年(1988年)に、越谷市制30周年記念事業の一環として名づけられた市道の愛称。南荻島の中心地点(荻島小学校)から越谷街道と末田大用水(すえだだいようすい)が交わる交差点(大石橋)まで(上の地図参照)
※1 地図はGoogleマップ( 荻島仲良し通り )を加工して作成
末田大用水と末田用水
末田大用水は、末田用水(すえだようすい)とも呼ばれているが、本記事では、「末田大用水」と表記する。
主な見学先

今回は、大石橋から荻島小学校に向かって荻島仲良し通り沿いを巡った。
主な見学先は、◇西新井山王神社◇末田大用水◇ひやみず観音堂◇ひやみず橋◇下手堰◇二基の石塔◇庚申塔◇南荻島中組集会所(明王院跡)……の八箇所。
起点|大石橋

2025年2月24日・10時50分。起点の大石橋(おおいしばし)着。越谷街道と末田大用水が交差する地点で、大石橋は、末田大用水に架かる橋で、越谷街道を通している。
「荻島仲良し通り」の標識

道路脇に「荻島仲良し通り」の標識が立っている。
標識から末田用水の上流(北)を望むと、50メートル先の右手(用水路脇)に、西新井山王神社(さんのうじんじゃ)の赤い鳥居と社(やしろ)が見える。
まずは、山王神社に向かった。
暗渠

大石橋から西新井山王神社まで、末田大用水は、暗渠(※2)になっている。
※2 暗渠(あんきょ)とは、蓋をされて外からは流れが見えなくなってしまった川や水路のこと。土の中に埋められてしまって水路跡だけが残っている場合も暗渠と呼ばれている。
西新井山王神社

山王神社着。社(やしろ)は、西新井の最北東に位置している。
三猿庚申塔|ご神体

山王社の建立は、由来碑では、ご神体(三猿庚申塔)が造塔された江戸前期・延宝6年(1678)としている。
石塔と石碑

鳥居の脇にある二基の石塔は、江戸後期・文化9年(1812)造塔の青面金剛像庚申塔と、江戸中期・明和3年(1766)建立の石橋供養塔。
祠の横には、明治32年(1899)に建立された、山王神社の由来が刻まれた由来碑(山王神社碑)が立っている。
新旧写真

西新井山王神社今昔
上の白黒写真は、今から50年前、昭和50年代に撮影されたと思われる西新井山王神社。出典は越谷市デジタルアーカイブ(※3)
下の写真は今回、ボクが撮影した同じ場所からの風景。
鳥居や社・石塔などの配置は換わっていない。社の両脇にあった松の木などは今は伐採されている。後方に広がる田畑の景色も当時の面影をわずかながらに保っている。
※3 白黒写真の出典…越谷市デジタルアーカイブ「西新井山王社と鳥居」
西新井山王神社については別記事で詳しく解説している。
関連記事
越谷市・西新井山王神社の三猿庚申塔のほか石仏と由来碑を調べた。場所は、越谷街道と荻島仲良し通りの交差点から北40メートル、末田用水沿いにある。
移動

山王神社をあとに、末田大用水を右に見ながら、荻島仲良し通りを北に進む。末田大用水は、ここからは暗渠ではなく、開渠(※4)になった。
※4 開渠(かいきょ)とは、用水路などで蓋をされていない(暗渠になっていない)水路のこと。
前方右手に橋が見えてきた。
山王橋|末田大用水

山王橋から末田大用水の上流を望む
末田大用水にかかるこの橋は山王橋(さんのうばし)。西新井の最北にあたる。山王橋を過ぎると南荻島の地に入る。荻島仲良し通りの左手(西側)は北後谷(きたうしろや)
移動

山王橋を過ぎて、荻島仲良し通りを100メートルほど進むと、交差点にぶつかる。左右に延びているのは越谷浦和バイパス(国道463号)
右側の末田大用水は、交差点の20メートル手前から暗渠になって越谷浦和バイパスの下をくぐり、交差点を越えた20メートルほど先で、再び開渠になる。
二基の石塔と堂舎

信号を渡って、荻島仲良し通りを直進。前方左手に、二基の石塔と、堂舎のある墓地が見えてきた。堂舎のうしろは墓地(ひやみず共同墓地)になっている。